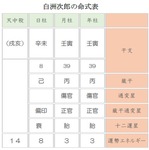美空ひばり、手塚治虫、松田優作、竹下登の金庫番……。平成元年を象徴した6人の最期
昭和から平成へと移りゆく「時代」の風景が見えてくる「平成の死」を振り返る。
■世界一豊かなアメリカでの成功を夢見た大スター
この年には、松田優作の死もあった。主治医によれば、昭和63年9月の時点で「ガンは膀胱の4分の1ほどを冒して」おり、告知も行なわれた。しかし、松田はオーディションで射止めたハリウッドデビュー作『ブラック・レイン』の撮影中だったため、手術をしないことを選択。妻・松田美由紀にも翌春まで秘密にし、話した際も軽症だと嘘をついたという。
そして、映画は日米両国でヒットする。が、日本での公開日、ついに緊急入院。主治医によれば「相当進行していて、尿もつまって出ないような状況」だった。そのまま病院の外に出ることなく、1ヶ月後の11月6日、40歳で他界するのである。
最晩年の松田は、鉄板焼きの海老を見ても失われた命への感謝を吐露する一方で、本格的ハリウッド進出への意欲も保ち続けていた。死の予感を強くしながらも、俺が死ぬはずがない、死んでたまるかという気持ちをそれ以上に持ち合わせていた印象を受ける。その精神性はどこから来ていたのか。ひとつ、着目したいのが彼の出自だ。
松田は在日韓国人の母と日本人の父のあいだに生まれた私生児で、デビュー時の戸籍名は「金優作」だった。帰化申請しても通らず、高校時代には米国に留学して現地の国籍取得を目指したものの挫折。それが『太陽にほえろ!』で人気俳優となったことで、チャンスが訪れる。
「僕はいまテレビの人気番組に出ているのですが、国籍が違うとわかったら、視聴者の皆さんにガッカリされてしまうでしょう」
そんな内容の帰化申請動機書を法務大臣に提出し、晴れて日本人・松田優作に。最初の妻である松田美智子は、この出来事を機に「言動に自信を持ち、性格も明るくなった」と、明かしている。ただ、子供時代のことは「ほとんど話さない人でした」とも。そのコンプレックスは根深く、ハングリー精神や承認欲求につながってもいたのだろう。また、国籍上の屈折を抱える者が世界一豊かな米国での成功でそれを一気に超えようとするのもありがちなパターンだ。松田の壮絶な死は、日韓の複雑な歴史にも思いを馳せさせるものだった。
改元から半月後に、16歳で夭折したアイドルもいる。バイク事故による脳内出血がもとで亡くなった高橋良明だ。ジャニーズ事務所が独占しつつあった男性アイドルシーンにおいて、児童劇団出身ながら、歌をヒットさせ、ドラマ『オヨビでない奴!』に主演するなど活躍していた。
平成最初の大河ドラマ『春日局』でも、序盤にヒロインの兄役で登場。そのあとは、ドラマ『ツヨシしっかりしなさい』の主演が決まっていた。彼の死により、主役は森且行が務めることになる。SMAPでは初の連ドラ主演で、彼らのCDデビューはその2年後だ。高橋は男性アイドル史の節目に、無邪気な印象を残して散っていった。
KEYWORDS:
『平成の死: 追悼は生きる糧』

鈴木涼美さん(作家・社会学者)推薦!
世界で唯一の「死で読み解く平成史」であり、
「平成に亡くなった著名人への追悼を生きる糧にした奇書」である。
「この本を手にとったあなたは、人一倍、死に関心があるはずだ。そんな本を作った自分は、なおさらである。ではなぜ、死に関心があるかといえば、自分の場合はまず、死によって見えてくるものがあるということが大きい。たとえば、人は誰かの死によって時代を感じる。有名人であれ、身近な人であれ、その死から世の中や自分自身のうつろいを見てとるわけだ。
これが誰かの誕生だとそうもいかない。人が知ることができる誕生はせいぜい、皇族のような超有名人やごく身近な人の子供に限られるからだ。また、そういう人たちがこれから何をなすかもわからない。それよりは、すでに何かをなした人の死のほうが、より多くの時代の風景を見せてくれるのである。
したがって、平成という時代を見たいなら、その時代の死を見つめればいい、と考えた。大活躍した有名人だったり、大騒ぎになった事件だったり。その死を振り返ることで、平成という時代が何だったのか、その本質が浮き彫りにできるはずなのだ。
そして、もうひとつ、死そのものを知りたいというのもある。死が怖かったり、逆に憧れたりするのも、死がよくわからないからでもあるだろう。ただ、人は自分の死を認識することはできず、誰かの死から想像するしかない。それが死を学ぶということだ。
さらにいえば、誰かの死を思うことは自分の生き方をも変える。その人の分まで生きようと決意したり、自分も早く逝きたくなってしまったり、その病気や災害の実態に接して予防策を考えたり。いずれにせよ、死を意識することで、覚悟や準備ができる。死は生のゴールでもあるから、自分が本当はどう生きたいのかという発見にもつながるだろう。それはかけがえのない「糧」ともなるにちがいない。
また、死を思うことで死者との「再会」もできる。在りし日が懐かしく甦ったり、新たな魅力を発見したり。死は終わりではなく、思うことで死者も生き続ける。この本は、そんな愉しさにもあふれているはずだ。それをぜひ、ともに味わってほしい。
死とは何か、平成とは何だったのか。そして、自分とは――。それを探るための旅が、ここから始まる。」(「はじめに」より抜粋)